煮物を作るとき、「ちゃんと煮込んだはずなのに、なんだか味がしみていない…」と感じたことはありませんか?
実は、煮物の“味しみ”にはちょっとしたコツやタイミングが関係しています。煮込む時間を長くするだけでは、素材の中心までしっかり味を入れるのは難しいこともあるんです。
特に、にんじんや大根、こんにゃくなどの根菜類や繊維の多い食材は、煮汁が中まで届くのに時間がかかります。
また、煮汁の濃さや火加減、冷まし方によっても仕上がりに大きな差が出るのが煮物の難しいところ。
この記事では、そんな“味がしみない問題”を解決するための、プロも実践している「味しみテクニック」をご紹介します。
家庭のキッチンでもすぐに試せる方法ばかりなので、ぜひ参考にしてみてください!
✅ コツ① 冷ますことで味がしみる“温度のマジック”を活用
煮物にしっかり味をしみこませる最大のポイントは、「煮たあとに一度冷ますこと」です。
なぜなら、食材は冷めるときに煮汁を内部に吸い込む性質があるから。これは科学的にも証明されていて、「温度が下がるときに素材の細胞の隙間が閉じて、煮汁を引き込む」と言われています。
たとえば、大根の煮物を例にすると、煮立てた直後は表面にしか味がついておらず、中心部分はまだ白っぽくて味がぼんやりしがちです。
でも、一晩寝かせて翌日に食べると、芯まで味がしみ込んでいて感動する美味しさになりますよね。
短時間で味をしみこませたいときは、煮たあとに鍋ごと冷水や保冷剤で冷やす「急冷」もおすすめです。
冷蔵庫で一晩置くより時短で効果的に味が入るので、忙しい日の調理にも役立ちます。
「煮物は冷ましてからが本番」——これはプロの料理人も口をそろえて言う鉄則。
温度の変化を味方につけることで、あなたの煮物はワンランク上の仕上がりになりますよ!
煮物は一度冷ますと味が染み込みます。
そのまま保存できる耐熱ガラス容器があると、
翌日の温め直しも楽で衛生的です。
✅ コツ② 落とし蓋で煮汁を循環させる
煮物を作るとき、「落とし蓋」を使っていますか?
じつは、味しみの良し悪しに大きく関わるのがこの落とし蓋なんです。
落とし蓋とは、鍋の中の食材の上に直接のせる小さめの蓋のこと。
これを使うことで、煮汁が全体にムラなく行き渡り、食材一つひとつに味が均等に染み込みやすくなります。
ポイントは「煮汁の対流を助ける」こと。
普通に蓋をして煮るだけでは、鍋の底にある食材にばかり味が入りがちですが、落とし蓋をすると、煮汁が表面にもかかり、まるで全体が“お風呂”につかっているような状態に。
また、煮汁の蒸発も抑えられるため、短時間でしっかり味が入るんです。
キッチンペーパーやアルミホイルでも代用OK!
市販の木製やシリコンの落とし蓋がないときは、ペーパーで落とし蓋を作れば同じ効果が得られます。
「煮崩れ防止」や「照りを出す」効果もあり、一石三鳥の落とし蓋テク。
手間いらずで味しみ力がグンと上がるので、ぜひ次回の煮物から取り入れてみてくださいね。
✅ コツ③ 味付けは“二段階”で!序盤は薄味に
煮物の味がしっかりしみない理由の一つに、「最初から味を濃くつけすぎている」という落とし穴があります。
実はこれ、初心者にありがちなミス。煮始めの段階で味を濃くすると、食材の表面ばかりに味がついて、中までは届きにくくなるのです。
そこでおすすめなのが「味付けの二段階方式」。
まずは控えめな味付けで煮始めて、火が通ってきた段階や冷める前後で味を調整するのがポイントです。
たとえば、煮汁を作るときに最初は通常のレシピの8割程度の調味料にとどめ、
煮終わったあとに味見して「ちょっと薄いかな?」と思ったら、追い醤油やみりんなどで整えるのがベスト。
この方法をとることで、
- 表面ばかりしょっぱい
- 中は無味に近い
といった失敗を防げますし、味の濃淡が自然に整って、全体的にまろやかな煮物に仕上がります。
また、煮物は冷めると味が濃く感じやすくなるため、仕上がり直後はやや薄めでもOK。
「時間を味方につける」ことも、味しみ煮物の大切なコツです。
✅ コツ④ 具材ごとの火の通り方を意識する
「同じ鍋で煮たのに、にんじんは硬くて味がしみてないのに、じゃがいもは崩れそう…」なんて経験はありませんか?
これは、具材によって火の通りやすさ・味のしみにくさが違うからなんです。
たとえば、
- 根菜(大根・にんじん・ごぼう)は火が入りにくく、味もしみにくい
- こんにゃく・ちくわなどの練り物は味が入りやすい
- じゃがいもやかぼちゃは煮崩れやすく、長時間加熱に不向き
この特性を知らずにすべて一緒に煮ると、一部の食材だけが中途半端な仕上がりになってしまいます。
そこでおすすめなのが、
- 火の通りにくい野菜は先に煮る
- やわらかくなりすぎる具材は途中で加える
- 下茹でして火の通りをそろえる
などの「時間差調理」テクニックです。
さらに、味が入りにくい食材(特に大根やこんにゃく)は切り方にも工夫を。
面取りをしたり、隠し包丁を入れて表面積を増やすと、煮汁が入りやすくなります。
具材ごとにベストなタイミングで鍋に投入することで、見た目も味もしっかり整った“味しみ煮物”に仕上がりますよ!
✅ まとめ|味しみ煮物は「段取りと温度」がカギ
煮物を美味しく仕上げるには、ただ煮込むだけでは足りません。
今回ご紹介したように、「冷ます」「落とし蓋を使う」「味付けの順番」「具材ごとの火加減」といったちょっとした工夫こそが、“味しみ”の決め手になります。
とくに重要なのが「温度」と「時間」。
熱々のまま食べてしまうと、実はまだ味が染みきっていないことも多く、
冷めていく過程でじわっと煮汁が内部にしみ込むという仕組みを知っておくと、煮物の出来が大きく変わります。
また、煮物は一度に多めに作って、翌日以降に食べるのもおすすめ。
日が経つごとにさらに味がなじみ、まさに“ごはんが進むおかず”に進化していきます。
手間がかかるように思えるかもしれませんが、基本のコツを知っておけば、
忙しい日でも“味しみバッチリ”な煮物を無理なく作ることができます。
ぜひ、今日の一品から「味しみテクニック」を取り入れてみてくださいね!
食材を事前に柔らかくしておくと、味がぐっと染みやすくなります。
レンジでサッと火が通せるシリコンスチーマーがあると便利です。
ムラなく加熱できて、煮物の下ごしらえに最適!
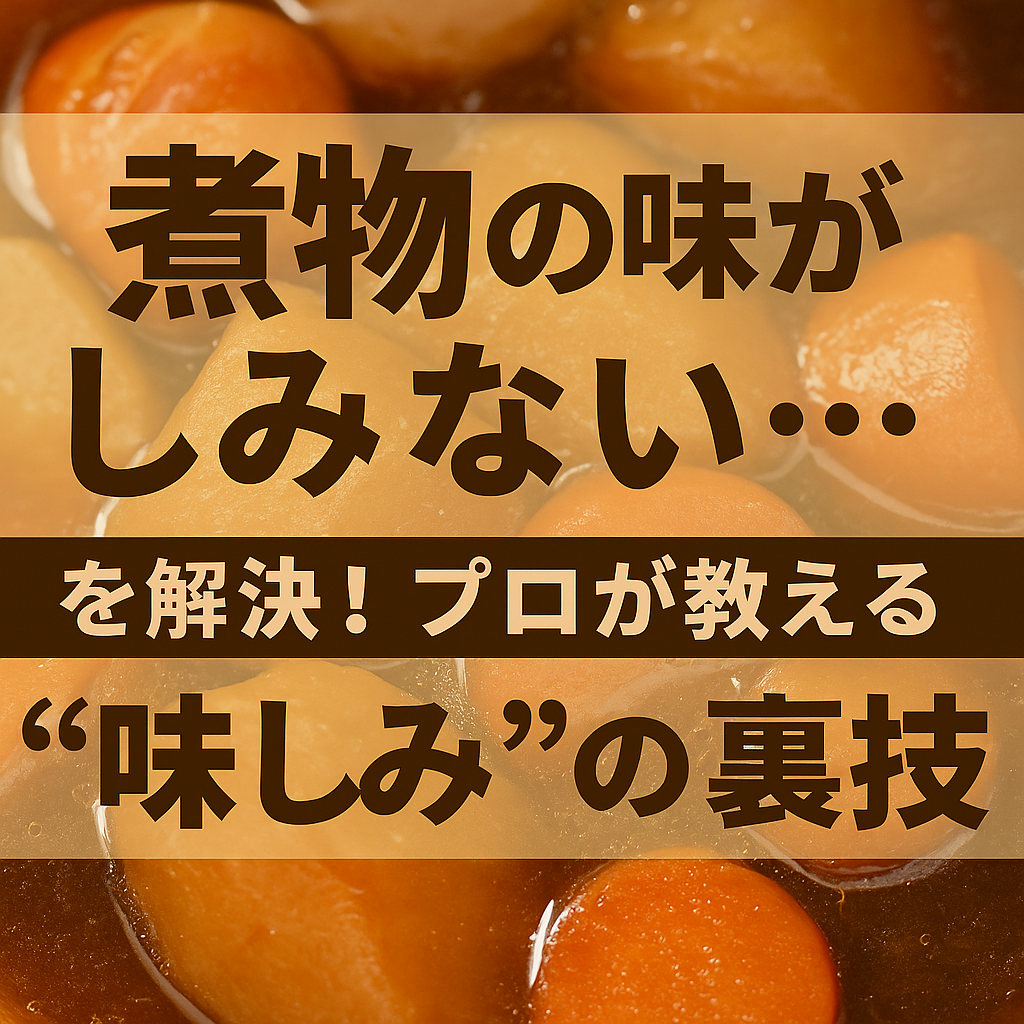
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4eb45c10.b81d6055.4eb45c11.376630dc/?me_id=1309659&item_id=10146426&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcolorfulbox%2Fcabinet%2Fmaker_kinto8%2F421232.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4eb459c8.8010c191.4eb459c9.9e8ee836/?me_id=1266479&item_id=10002059&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fiwaki-kitchenshop%2Fcabinet%2Fproduct_page%2Fimgrc0094149136.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4eb45ef6.2647d41d.4eb45ef7.064d6064/?me_id=1357621&item_id=10617116&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyamada-denki%2Fcabinet%2Fa07000364%2F6612636019.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4eb46425.131fb0bf.4eb46426.806be1b3/?me_id=1436683&item_id=10039182&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fail-shops2%2Fcabinet%2Fr_2025101505%2F20251015220451_109_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
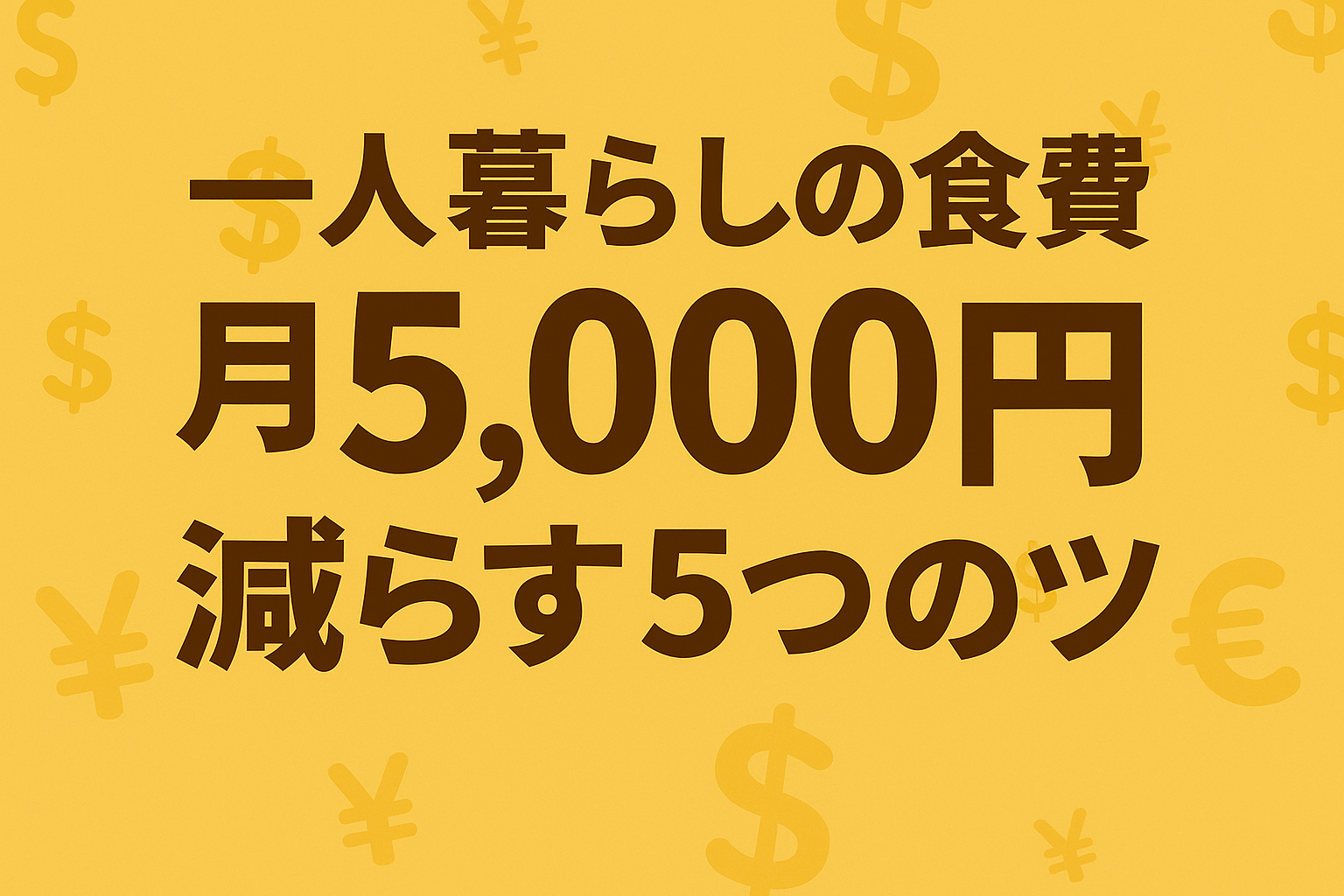
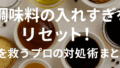
コメント